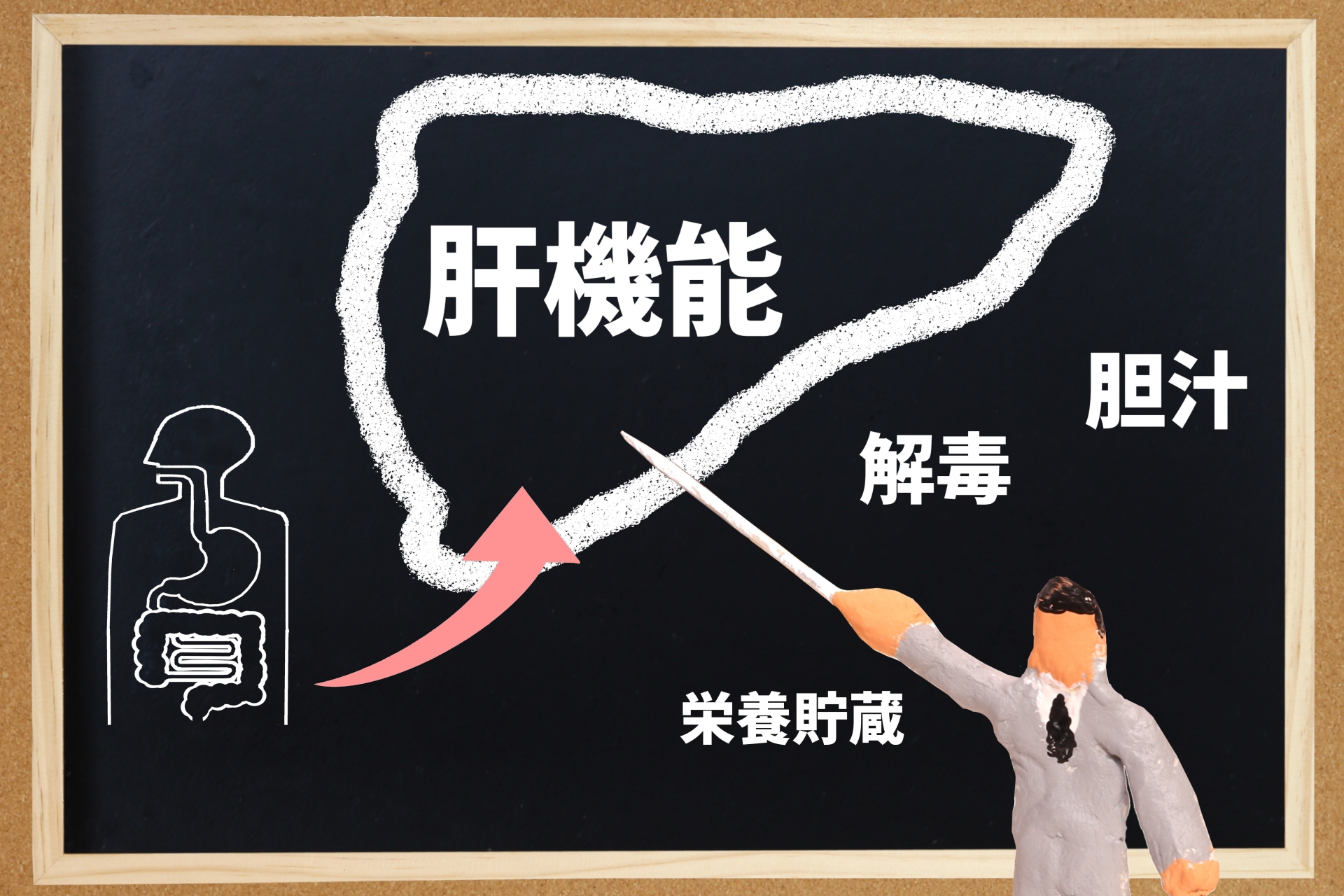2025年11月10日

EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、私たちの健康維持に不可欠な栄養素として、広く知られるようになりました。
これらは「オメガ3(n-3系)脂肪酸」と呼ばれる脂質の一種で、特に青魚に豊富に含まれています。
しかし、「健康に良い」とわかっていても、「具体的に1日どれくらい摂ればよいのか」については、様々な情報があり混乱しやすいかもしれません。
この記事では、日本の厚生労働省や国際的な専門機関が示す科学的根拠に基づき、一般の方が1日に摂取すべきEPA・DHAの量について解説します。
EPAとDHAとは? なぜ必要なのか?
まず、EPAとDHAがどのような働きをするのかを簡単に理解することが重要です。
体内で作れない「必須脂肪酸」
EPAとDHAは、人間の体内で作ることができない(または作られても非常に効率が悪い)ため、食事から摂取する必要がある「必須脂肪酸」に分類されます。
EPAの主な働き
EPAは、血液や血管の健康維持に深く関わっています。
主な働きとして、血液中の中性脂肪(トリグリセリド)値を低下させる作用、血液を固まりにくくし(抗血小板作用)、血液の流れをスムーズにする作用、そして体内の炎症を抑える作用などが報告されています。
これにより、動脈硬化や心筋梗塞などの循環器系疾患のリスクを低減する効果が期待されています。
DHAの主な働き
DHAは、脳や目の網膜といった神経系の組織に多く含まれる成分です。
特に、脳の神経細胞(ニューロン)の機能を維持し、情報伝達をスムーズにするために重要です。
胎児や乳幼児の脳の発達に不可欠であるほか、成人においても認知機能の維持に関与する可能性が研究されています。
日本におけるEPA・DHAの摂取目標量
日本人の健康維持・増進、生活習慣病予防のために、厚生労働省は「日本人の食事摂取基準」を5年ごとに策定しています。
EPAとDHAの摂取量について、最も信頼できる日本の基準はこれに基づいています。
結論:1日1,000mg(1g)以上が目標
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、EPAおよびDHAの摂取について、18歳以上の男女ともに1日あたり1,000mg(=1g)以上摂取することが望ましい(目標量)と設定されています。
「目標量」とは?
「日本人の食事摂取基準」では、栄養素ごとに「推定平均必要量」「推奨量」「目安量」「目標量」などが設定されます。
EPAとDHA(および同じオメガ3であるα-リノレン酸)を含むn-3系脂肪酸については、生活習慣病(特に心血管疾患)の予防を目的として「目標量」が設定されています。
この1,000mg/日という数値は、日本人を対象とした研究(コホート研究)などに基づき、心血管疾患のリスク低減が期待できる量として設定されたものです。
補足:n-3系脂肪酸全体の目標量
食事摂取基準では、EPA、DHA、そして植物油(えごま油、亜麻仁油など)に含まれるα-リノレン酸をすべて含んだ「n-3系脂肪酸」全体の目標量も設定されています。
これは成人(18~49歳)で男性2.0g/日、女性1.6g/日など、年齢性別で細かく定められています。
1,000mg/日のEPA・DHAは、このn-3系脂肪酸全体の目標量を達成するための重要な内訳となります。
国際的な摂取推奨量
日本の「1日1,000mg」という目標量は、世界的に見てもどのような位置づけなのでしょうか?
WHO(世界保健機関)および FAO(国連食糧農業機関)
2010年の報告書において、心血管疾患のリスク低減のため、一般成人は1日にEPAとDHAを合計で250mg〜500mg摂取することを推奨しています。
AHA(米国心臓協会)
健康な成人(心疾患予防): 1週間に2回(特にサケ、サバ、イワシなどの脂ののった魚)の魚を食べることを推奨しています。これは1日あたり約250mg〜500mgのEPA・DHA摂取に相当します。
冠状動脈性心疾患(心筋梗塞など)の既往がある人: 1日にEPAとDHAを合計で約1,000mg(1g)摂取することを推奨しています。
中性脂肪(トリグリセリド)が高い人: 医師の管理下で、1日に2,000mg〜4,000mg(2g〜4g)のEPA・DHA(多くはサプリメントとして)の摂取が治療選択肢となり得るとされています。
EFSA(欧州食品安全機関)
一般の健康な成人に対し、心血管系の健康維持のために1日にEPAとDHAを合計で250mg摂取することを推奨しています。
日本の目標量は比較的高め
日本の目標量(1,000mg/日)は、欧米の一般成人向け推奨量(250mg/日)と比較して高めに設定されています。
これは、伝統的に魚食文化があり、魚の摂取量が多い日本人の食生活と、日本人を対象とした研究成果に基づいているためです。
特に摂取が推奨される人
すべての人に1,000mg/日が推奨されますが、特に以下の人々は意識的な摂取が求められます。
妊婦・授乳婦
胎児や乳児の脳や網膜の発達にとって、DHAは極めて重要です。
• 日本の食事摂取基準(2020年版)
妊婦および授乳婦は、通常の成人の目標量に加えて、n-3系脂肪酸(DHAを豊富に含む)を多めに摂ることが推奨されています。(例:18~49歳女性のn-3系脂肪酸目標量1.6g/日に対し、妊婦は1.8g/日、授乳婦は2.0g/日)
世界的な基準(後述)も参考にし、DHAを意識して摂取することが望まれます。
• WHO(世界保健機関)の推奨
妊婦・授乳婦は、1日にEPAとDHAを合計で300mg以上摂取し、そのうちDHAを200mg以上摂取することを推奨しています。
魚を食べる習慣があまりない人
現代の食生活では、肉類中心で魚を食べる機会が週に1回未満という人も少なくありません。
日本の平均的なEPA・DHA摂取量は目標量を下回っている可能性が指摘されており、特に若年層で不足しがちです。
中性脂肪値が気になる人・心血管疾患のリスクが高い人
前述のAHAの推奨にもある通り、すでに心血管疾患のリスクが高い、または中性脂肪値(TG)が基準値を超えている場合、1,000mg/日以上の摂取が有益である可能性が高いため、医療機関を受診し、医師から指導を受けることをお勧めします。
1,000mgのEPA・DHAを食品で摂る方法
1,000mg(1g)のEPA・DHAは、どのくらいの魚に含まれているのでしょうか。目安として、「1週間に2〜3回、青魚を1人前食べる」ことで達成できる量です。
以下は、調理後の魚1食分(約80g〜100g)あたりに含まれるEPAとDHAの合計量のおおよその目安です。(数値は食品の個体差や調理法により変動します)
|
魚の種類 |
1食分(約80g)あたりのEPA・DHA合計(目安) |
達成度 |
|
サバ(鯖) |
約2,000mg 〜 3,000mg |
◎ 余裕で達成 |
|
サンマ(秋刀魚) |
約1,800mg 〜 2,500mg |
◎ 余裕で達成 |
|
ブリ(鰤) |
約1,500mg 〜 2,200mg |
○ 達成 |
|
イワシ(鰯) |
約1,200mg 〜 2,000mg |
○ 達成 |
|
アジ(鯵) |
約800mg 〜 1,400mg |
○ ほぼ達成 |
|
サケ(鮭・養殖) |
約1,000mg 〜 1,800mg |
○ ほぼ達成 |
|
マグロ(トロ) |
約1,500mg 〜 2,800mg |
○ 達成 |
|
マグロ(赤身) |
約100mg 〜 300mg |
△ 不足 |
|
タラ(鱈) |
約150mg 〜 250mg |
△ 不足 |
ご覧の通り、サバ、サンマ、ブリ、イワシといったいわゆる「青魚(光り物)」や、脂ののったサケ(サーモン)を1人前食べれば、1日の目標量1,000mgを十分に満たすことができます。
アジも優秀な供給源です。マグロは赤身よりも脂の多いトロの部分に多く含まれます。 調理が難しい場合は、サバやイワシの缶詰(水煮や味噌煮)でもEPA・DHAを効率よく摂取できます。
摂取に関する注意点
EPA・DHAは安全性の高い栄養素ですが、いくつか注意点があります。
上限量(耐容上限量)について
現在のところ、通常の食事から摂取する範囲では、過剰摂取による健康被害が起こる可能性は低いとされています。
日本の食事摂取基準(2020年版)
EPAおよびDHA(およびn-3系脂肪酸)について、明確な「耐容上限量(これ以上摂ると健康被害のリスクが上がる量)」は設定されていません。
ただし、EPA・DHAのサプリメントを併用する場合、n-3系脂肪酸全体の摂取量が非常に多くなる可能性があり、注意が必要としています。
国際的な見解(EFSAなど)
欧州食品安全機関(EFSA)は、サプリメントからのEPA・DHAの追加摂取について、1日合計5,000mg(5g)までであれば、長期的に摂取しても一般成人において安全上の懸念(出血リスクの増加など)は生じないとしています。
サプリメント利用時の注意
食事から魚を摂るのが難しい場合、サプリメント(健康食品や医薬品)を利用する選択肢もあります。
ただし、EPA・DHAは脂質であるため酸化しやすい性質があります。
品質管理が信頼できる製品を選ぶことが重要です。
医薬品との相互作用
EPA・DHAには血液を固まりにくくする作用(抗血小板作用)があるため、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬ワルファリンなど)や抗血小板薬(アスピリンなど)を服用している人は、高用量のEPA・DHA(特に1日数gレベル)をサプリメントで摂取すると、出血傾向が強まる可能性があります。
該当する方は、必ず主治医に相談してください。
妊婦の魚摂取と水銀
魚はEPA・DHAの優れた供給源ですが、一部の大型魚には食物連鎖を通じて「メチル水銀」が蓄積されている可能性があります。
メチル水銀は胎児の発達に影響を与える可能性があるため、厚生労働省は妊婦に対し、一部の魚の摂取量に注意喚起をしています。
注意が必要な魚(例): キンメダイ、メカジキ、クロマグロ、メバチマグロなど。
安全性が高い魚(例): サケ、アジ、サバ、イワシ、サンマ、カツオ、ブリなど。
EPA・DHAの摂取源として推奨されるアジ、サバ、イワシ、サンマ、サケなどは、水銀蓄積のリスクが低い魚ですので、これらを選んでバランス良く食べることが推奨されます。
まとめ
EPA・DHAの摂取に関する科学的根拠に基づく要点は以下の通りです。
1.日本の目標量: 健康な成人は、心血管疾患予防のため、EPAとDHAの合計で1日1,000mg(1g)以上の摂取が推奨されます。
2.国際的な最小推奨量: WHOなどは、健康維持のために少なくとも1日250mgの摂取を推奨しています。
3.特定の対象者: 妊婦・授乳婦は、胎児・乳児の脳の発達のためにDHAを意識して摂取する必要があります。
4.達成方法: 目標の1,000mgは、サバ、サンマ、イワシ、ブリ、サケなどの脂ののった魚を1人前(約80g)食べることで達成可能です。週に2〜3回、魚料理を取り入れることが現実的な目安です。
5.安全性: 食事からの摂取で過剰になる心配は低いですが、抗凝固薬などを服用中の方が高用量のサプリメントを摂る場合は、医師への相談が必要です。
まずは、日本の目標である「1日1,000mg」を目指し、日常の食生活に上手に青魚を取り入れてみてください。
主な出典
・厚生労働省(2019).「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
(特に「脂質」の章、n-3系脂肪酸の項目)
・厚生労働省. 「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」(2010年改訂)
・World Health Organization (WHO) / Food and Agriculture Organization (FAO) (2010). Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition.
・American Heart Association (AHA) (2019). Triglycerides and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association.
・American Heart Association (AHA). Fish and Omega-3 Fatty Acids. (Web resource)
・European Food Safety Authority (EFSA) (2012). Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and docosapentaenoic acid (DPA).
大阪府吹田市長野東19番6号
千里丘かがやきクリニック
有光潤介