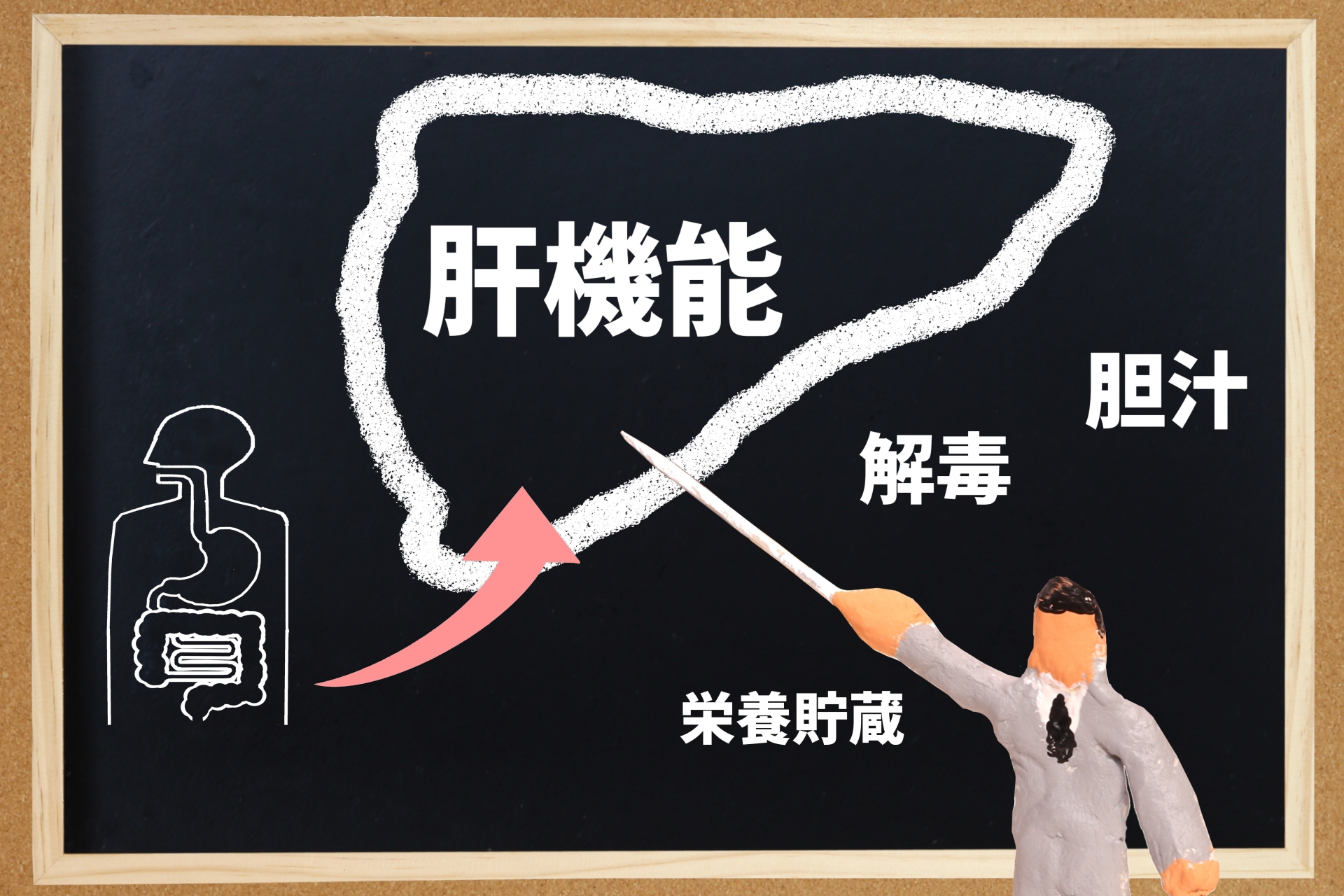2025年11月16日

インフルエンザの予防接種を受けるたびに「今回は痛いかな?」「痛くないといいな」とドキドキしますよね。
そして、不思議なことに、同じ予防接種のはずなのに「すごく痛かった!」という時と、「え、もう終わったの?」と拍子抜けするほど痛くなかった時がある。この違いは一体なぜなのでしょうか。
先生や看護師さんの腕が違うから? もちろんそれもあります。 でも、一番大きな理由は、私たちの体に備わっている「痛点」というセンサーに、針が「当たった」か「当たらなかった」か、という「運」の要素が強いのです。
私たちの体には、外の世界や体の中の様子を知るための「センサー(受容器)」がたくさんあります。
- 指先で触れたものの硬さや形を感じる「触点(しょくてん)」
- 熱いお風呂に入った時に「熱い」と感じる「温点(おんてん)」
- 冷たいかき氷で「冷たい」と感じる「冷点(れいてん)」
そして、これらと同じように、「体に危険が迫っている!」と知らせるための専門のセンサーがあります。それが「痛点(つうてん)」です。
痛みは、私たちにとって不快なものですが、実は「体からの重要な警告(アラーム)」です。
もし痛みを感じなければ、熱いやかんに触り続けて大やけどをしたり、ケガをしても気づかずに悪化させてしまったりするでしょう。
痛みは、私たちが生き延びるために欠かせない感覚なのです。
「痛点」の正体とは?
では、その「痛点」とは、具体的にどんなものなのでしょうか。
「点」ではなく「神経の先端」
「痛点」という名前から、皮膚の上に「痛みを感じる小さな点」がポツポツと存在しているようなイメージを持つかもしれません。昔の研究では、皮膚を細い針でつついて痛みを感じる場所を地図のように記録したため、このように呼ばれるようになりました。
しかし、現在の研究では、その正体はもう少し複雑なことがわかっています。
私たちの皮膚のすぐ下(表皮と真皮の境界あたり)には、目に見えないほど細い神経が、まるで木の根っこや網の目のようにびっしりと張り巡らされています。
この網の目のように広がった神経の「先端(末端)」がむき出しになっており、これが「痛点」の正体です。専門的には「自由神経終末」と呼ばれます。
この神経の先端は、一定以上の強い刺激(針で刺される、強くつままれる、熱すぎるものに触れるなど)を受けると、「危険だ!」という電気信号を発生させ、その信号が脊髄(せきずい)を通って、一瞬で脳に送られます。
そして、脳がその信号を受け取って、初めて私たちは「痛い!」と感じるのです。
痛点には「ムラ」がある
ここが最も重要なポイントです。
この神経の先端(痛点)は、皮膚の表面に均一に分布しているわけではありません。
まるで、森の中の木の根っこが、ある場所には密集して生えているのに、別の場所にはまばらにしか生えていないのと同じです。
痛点がぎっしり密集している場所と、スカスカでまばらな場所があるのです。
敏感な場所(痛点が多い):指先、唇、顔など。
手先で危険なものに触れたり、大切な顔を守ったりするために、センサーが発達していると考えられています。
鈍感な場所(痛点が少ない):背中、お腹、太ももなど。
指先などに比べると、痛点の密度が低い傾向があります。
注射を打つ腕(肩の近くの三角筋や、上腕三頭筋あたり)も、もちろん痛点はありますが、その分布には個人差があり、同じ人でも右腕と左腕、さらに腕のほんの数ミリ違う場所でも、痛点の密度は異なっています。
なぜ予防接種の痛みに差が出るのか?
この「痛点のムラ」こそが、注射の痛みが毎回違う最大の理由です。
理由1:痛点の「当たり外れ」(運)
予防接種で使われる注射針の先端は、非常に細く、直径1mmにも満たないものです。
この細い針が、あなたの腕に刺さった瞬間を想像してみてください。
痛くなかった時
・針が刺さった場所が、たまたま痛点(神経の末端)が少ない「スカスカな場所」だった。
・針は、神経の網の目をうまくすり抜けて、組織の隙間に入っていきました。
・脳に送られる「痛い!」という信号が非常に弱かったため、ほとんど痛みを感じなかったのです。
すごく痛かった時
・針が刺さった場所が、たまたま痛点が「密集している場所」だった。
・運悪く、針の先端が神経の末端(痛点)に直撃してしまいました。
・神経は「とんでもない危険だ!」と判断し、非常に強い電気信号を脳に送りました。
・その結果、私たちは「すごく痛かった!」と感じるのです。
これは、道に落ちている画びょうを想像すると分かりやすいかもしれません。
体育館に画びょうが100個まかれていたとして、裸足で歩いた時に「踏んでしまう」か「踏まずに済む」かは、ほとんど運ですよね。
注射もこれと同じで、医療者がどれだけ熟練者でも、「ここには痛点があるから避けよう」と狙って避けることは不可能です。なぜなら、痛点は目に見えないからです。
毎回「痛点の地雷原」を歩くようなもので、たまたま地雷(痛点)を踏んでしまった時が「痛い注射」になるのです。
理由2:医療者の「技術」
もちろん、医療者の技術も痛みに関係しています。
刺すスピードと角度:
・経験豊富な医療者は、痛点を刺激する可能性を少しでも減らすため、適切な角度で、迷いなくスピーディーに針を刺します。
・針が皮膚を通過する時間が短ければ短いほど、神経が刺激される時間も短くなります。
・逆に、ゆっくりと針が入ってきたり、針先が皮膚の下で動いたりすると、それだけ多くの神経を刺激してしまい、痛みを感じやすくなります。
理由3:受ける側の「心理状態」
意外に思われるかもしれませんが、「心の持ちよう」も痛みの感じ方を大きく左右します。
緊張と恐怖:
・「痛いだろうな」「怖いな」と強く思っていると、体は戦闘態勢に入ります。
・筋肉がカチコチに緊張し、こわばってしまいます。硬くなった筋肉に針を刺すのは、柔らかい筋肉に刺すよりも余計な力が必要になり、抵抗が大きくなるため、痛みを感じやすくなります。
意識の集中:
・注射針の先端をじっと見つめたり、「今だ!」「来るぞ!」と痛みに意識を集中させすぎたりすると、脳は「痛みの信号」に対して非常に敏感になります。
・まるで、耳を澄ましている時に小さな物音が大きく聞こえるのと同じで、脳が痛みを「増幅」させてしまうのです。
リラックスと意識の分散:
・逆に、深呼吸をしてリラックスしたり、看護師さんと世間話をしたり、壁のポスターを眺めたりして、意識を注射からそらしていると、脳が痛みの信号を「重要でない」と判断しやすくなります。
・その結果、同じ強さの刺激でも、痛みを感じにくくなるのです。
理由4:薬液の種類や針の太さ
薬液の刺激:
ワクチンの種類によっては、薬液そのものが(pHや浸透圧の関係で)組織にしみたり、軽い炎症を起こしたりして、注入時に痛みを感じやすいものがあります。(インフルエンザワクチンなどで「薬が入ってくる時が痛い」と感じるのはこれが一因です)
針の太さ:
予防接種の種類によって、使う針の太さ(ゲージ)が決まっています。
当然ですが、針が太いほど、組織を傷つける面積が広くなり、痛点に当たる確率も高くなります。
注射の種類:
皮膚の浅いところに打つ「皮下注射」か、深い筋肉に打つ「筋肉注射」(コロナワクチンなど)かによっても、痛みの種類や、打った後の痛みの残り方(筋肉痛のような痛み)が変わってきます。
痛みを和らげるための「ちょっとした工夫」
痛点に当たるかどうかは「運」だとお伝えしましたが、それ以外の要因で痛みを減らす工夫はできます。
とにかくリラックスする
・注射を打つ方の腕や肩の力を、意識して「だらーん」と抜きましょう。
・「ふーっ」と息を吐いている瞬間に打ってもらうと、自然と筋肉の力が抜けます。
意識をそらす
・注射の針先を絶対に見ないこと。
・遠くの景色や、壁の時計、ポスターなどをぼんやり眺めましょう。
・医療者や付き添いの人と、全く関係のない話(「昨日のテレビ見た?」「今日の晩ごはん何にしよう?」など)をするのも非常に有効です。
「痛いのが苦手」と正直に伝える
我慢せず、「すごく痛いのが苦手(怖い)なんです」と先に伝えてみましょう。
医療者側も、「じゃあ、話しながらやりましょうか」「できるだけサッと終わらせますね」など、リラックスできるよう配慮してくれることが多くあります。

まとめ
予防接種の痛みが時によって違う理由を、まとめます。
最大の理由は「痛点」の当たり外れ(運)
「痛点」とは、皮膚の下に張り巡らされた「神経の先端(自由神経終末)」のこと。
この分布には「密集した場所」と「まばらな場所」がある。
針がたまたま「まばらな場所」をすり抜ければ痛くなく、たまたま「密集した場所」や神経に直撃すると痛い。
その他の要因
技術:刺すスピードや、薬液を注入するペース。
心理:緊張や恐怖は痛みを増幅させ、リラックスや「意識をそらすこと」は痛みを和らげる。
薬液:ワクチンの種類そのものが刺激性の場合もある。
痛みの正体は、体を守るための大切なアラームです。注射が痛いのは、体が「異物(針)が入ってきた!」と正常に反応している証拠でもあります。
次に注射を受ける時は、「痛点ガチャ(運試し)だな」と少し気楽に考え、なるべくリラックスして、意識を遠くに飛ばしてみてください。きっと、いつもより楽に乗り越えられるはずです。
大阪府吹田市長野東19番6号
千里丘かがやきクリニック
有光潤介