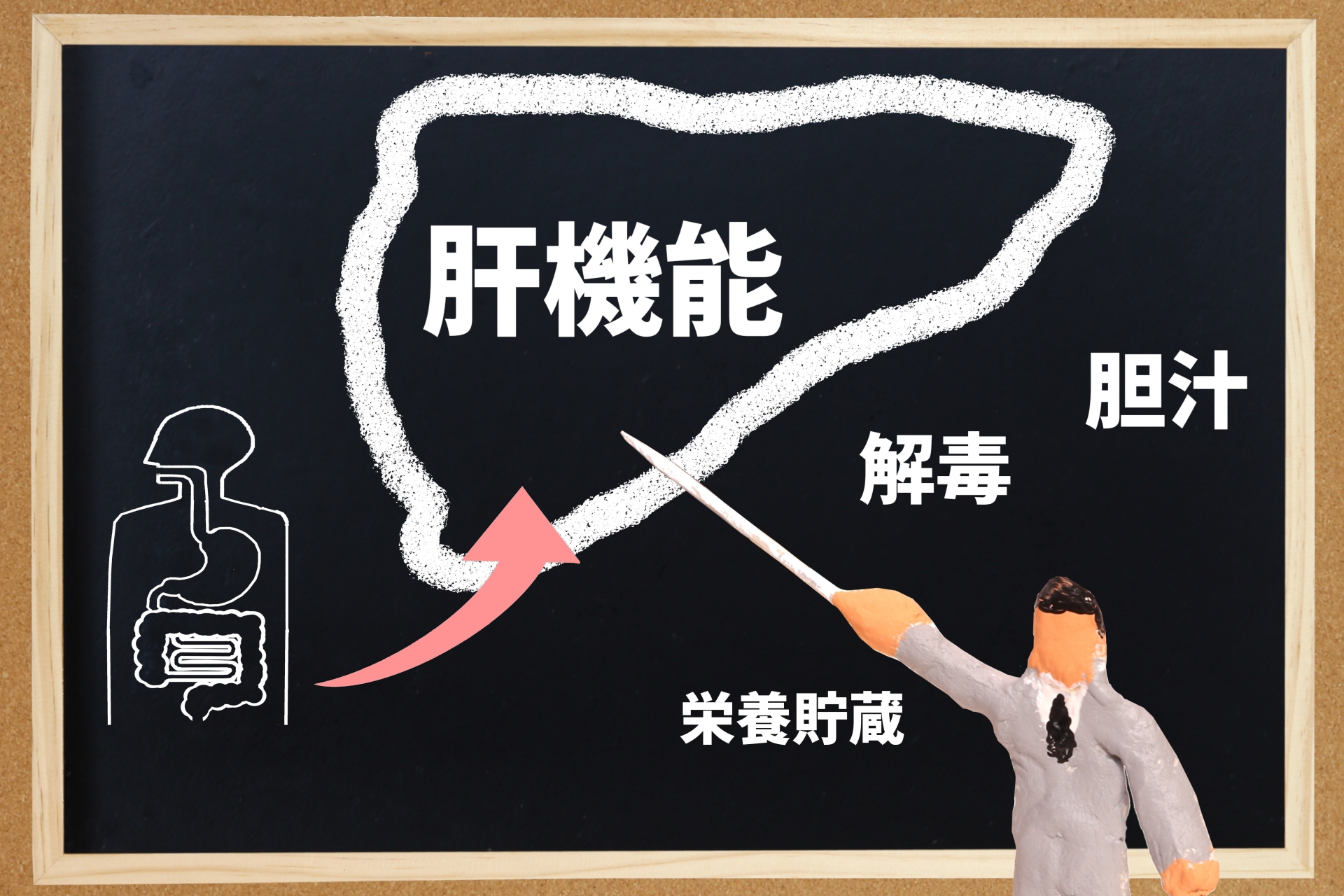2025年11月21日

私たちの血圧は、1日の中で大きく変動します。通常は昼間の活動時に高め、夜は副交感神経が優位になってリラックスするため低めになります。しかし、さまざまな理由によって 本来下がるはずの睡眠中に血圧が上がる ことがあります。
寝ている間に血圧が上がってしまう現象、あるいは本来下がるはずの血圧が下がらない状態は、専門的には「夜間高血圧」と呼ばれています。
これを放っておくと、心筋梗塞や脳卒中などのリスクを著しく高めるため、原因を調べて治療することがとても大切です。
本来の「正常な血圧」のリズムとは?
まず、異常を知るために「正常な状態」を理解しておきましょう。
私たちの体は、自律神経というシステムによって自動的にコントロールされています。
自律神経には、活動時に働く「交感神経(アクセル)」と、休息時に働く「副交感神経(ブレーキ)」の2つがあります。
昼間(活動時): 交感神経が活発になり、血圧を上げて全身に血液を巡らせ、活動できる状態にします。
夜間(睡眠時): 副交感神経が優位になり、心身をリラックスさせ、血圧を下げて血管や心臓を休ませます。
通常、夜寝ている間の血圧は、昼間に比べて10%〜20%ほど低くなるのが正常です。
これを医学用語で「ディッパー型(下がるタイプ)」と呼びます。
しかし、何らかの原因でこの切り替えがうまくいかず、夜になっても血圧が下がらない(ノンディッパー型)、あるいは逆に上がってしまう(ライザー型)ことがあり、これが非常に危険な状態なのです。

最大の原因その1:睡眠時無呼吸症候群(SAS)
夜間高血圧の最も代表的な原因が、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。
これは、寝ている間に気道(空気の通り道)が塞がり、呼吸が一時的に止まってしまう病気です。
「大きないびき」が特徴ですが、これがなぜ血圧を上げるのでしょうか。
体の中で起きている「緊急事態」
呼吸が止まるということは、体の中の酸素が不足するということです(低酸素血症)。 寝ている間に酸素不足になると、脳は「このままでは死んでしまう!」とパニック状態になります。
そこで、脳は無理やり体に酸素を巡らせようとして、自律神経を一気に「交感神経(興奮モード)」に切り替えます。
- 呼吸が止まり、酸素が減る。
- 脳が危険を感知し、交感神経を刺激する。
- 血管がキュッと収縮し、心拍数が上がる。
- 血圧が急上昇する。
睡眠時無呼吸症候群の人は、一晩に何十回、何百回と呼吸が止まります。
そのたびに体は「窒息しそうだ! 血を送れ!」と緊急指令を出し続けるため、寝ている間ずっと血管に強い圧力がかかり続けることになります。
本人は眠っているつもりでも、体は全力疾走しているのと同じくらい負担がかかっているのです。
上記の様に、睡眠時無呼吸症候群は血管内皮障害や酸化ストレスを引き起こすため、独立した動脈硬化リスク因子とされ、特に重症例ほどリスクが高くなります。
治療(CPAPなど)によって血管内皮機能や血圧が改善する報告もあり、動脈硬化進展の抑制が期待されます。
最大の原因その2:塩分の摂りすぎと「夜間の残業」
日本人にとって非常に多い原因が、「塩分の摂りすぎ」によるものです。
「塩分を摂ると血圧が上がる」というのは有名ですが、実は「夜間の血圧」と密接な関係があります。
これには腎臓(じんぞう)の働きが関わっています。

腎臓による「圧利尿」のメカニズム
腎臓は、血液中の余分な塩分(ナトリウム)と水分を濾過して、尿として体の外へ捨てる役割を持っています。
しかし、昼食や夕食で塩分を摂りすぎると、腎臓は日中のうちに全ての塩分を捨てきることができません。
血液中に塩分が残ったまま夜を迎えることになります。
血液中の塩分濃度が高いままだと体によくないため、体は寝ている間になんとかして塩分を排出しようとします。
この時、腎臓が塩分を尿として押し出すためには、血圧を高く保つ必要があるのです。
これを医学的に「圧利尿」と呼びます。
- 正常な場合: 日中に塩分が処理され、夜は腎臓も休める(血圧が下がる)。
- 塩分過多の場合: 夜になっても塩分が残っているため、血圧を上げて腎臓を「残業」させ、無理やり塩分を捨てさせる。
つまり、夜血圧が下がらないのは、「体が寝ている間に必死で塩分を捨てようとしているサイン」でもあるのです。特に、腎臓の機能が少し低下している高齢者や慢性腎臓病の方は、この傾向が顕著に表れます。
血液検査で、ナトリウム(Na)が145mEq/Lを超えている場合は注意が必要です。
治療としては、少量の利尿剤を投与することで、血圧が下がるだけでなく、夜間頻尿も改善します。
原因その3:自律神経の故障と糖尿病
血圧のコントロールセンターである「自律神経」そのものがうまく働かなくなることで、夜間の血圧が上がることがあります。その代表的な原因が糖尿病です。
神経障害によるスイッチの不具合
糖尿病が高血糖状態を長く続けると、全身の神経がダメージを受けます(糖尿病神経障害)。
自律神経も例外ではありません。
自律神経がダメージを受けると、「夜になったからリラックスモード(副交感神経)に切り替える」というスイッチ操作ができなくなります。
その結果、夜になっても昼間の興奮モード(交感神経)が解除されず、血圧が高いまま維持されてしまうのです。
また、高齢になると血管が硬くなる(動脈硬化)だけでなく、自律神経の働き自体も鈍くなるため、生理的に夜間の血圧が下がりにくくなる傾向があります。
原因その4:見落としがちな生活習慣と環境
病気だけでなく、私たちが日常的に行っている習慣や環境が、夜間の血圧上昇を招いているケースも多々あります。
過度な飲酒(アルコール)
「お酒を飲むとよく眠れる」というのは間違いです。 確かに、アルコールが入った直後は血管が拡張して一時的に血圧は下がります。
しかし、アルコールが体内で分解され、効果が切れてくる数時間後(ちょうど睡眠中や明け方)に、体は反動(リバウンド)を起こします。
アルコールの分解産物であるアセトアルデヒドや、離脱作用によって交感神経が強く刺激され、明け方に血圧が急上昇します。
また、アルコールはのどの筋肉を緩めて気道を塞ぎやすくするため、前述の「睡眠時無呼吸症候群」を悪化させるダブルパンチとなります。
寒さ(室温の低下)
冬場や冷房の効きすぎた部屋で寝ると、体は体温を逃がさないように血管を収縮させます。
血管が縮まれば、当然血圧は上がります。
特に冬の明け方、布団から出ている顔や首が冷気にさらされることで血圧が上がり、脳卒中のリスクが高まることが知られています。
ストレスと睡眠の質
強いストレスを感じていると、寝床に入っても脳が興奮状態を維持してしまいます。
また、不眠症や、頻尿で何度も目が覚める(夜間頻尿)状態も良くありません。
目が覚めるたびに交感神経が働き、血圧が上がってしまいます。「ぐっすり眠れない」こと自体が、高血圧の原因になるのです。
なぜ夜間高血圧は怖いのか?
ここまで原因を見てきましたが、夜間の高血圧が恐れられる最大の理由は、「血管と心臓に休まる時間がない」からです。
血管や心臓は、本来なら寝ている間に低い血圧でゆっくり休み、翌日の活動に備えて修復を行います。
しかし、夜間も血圧が高いままだと、24時間365日、常に高い圧力がかかり続けることになります。
これにより、血管の壁は厚く硬くなり(動脈硬化の進行)、心臓は筋肉が分厚くなって(心肥大)、ポンプ機能が低下していきます。
研究によると、昼間だけ血圧が高い人よりも、夜間に血圧が高い人の方が、脳卒中や心筋梗塞を起こすリスクが高いことが分かっています。
「健康診断(昼間の測定)では正常だったのに、突然脳卒中で倒れた」というケースの多くに、この隠れた「夜間高血圧」が関わっていると言われています。
夜間高血圧の対策について
当然のことながら、夜間高血圧を防ぐためには、その原因に応じた対策が必要です。
- 減塩(最重要): 夕食の塩分を控えることで、夜間の「圧利尿」を防ぎ、腎臓と血管を休ませることができます。また、カリウム(野菜や果物に含まれる)を摂取して塩分の排出を助けることも有効です。
- 肥満の解消と睡眠時無呼吸の治療: いびきがひどい場合や、日中の眠気が強い場合は、専門の医療機関(呼吸器内科など)を受診しましょう。CPAP(シーパップ)という治療機器を使うことで、劇的に血圧が下がることもあります。
- 節酒: 寝る直前の大量の飲酒は控えましょう。
- 快適な睡眠環境: 冬場は寝室が寒くなりすぎないよう、断熱や暖房を適切に活用しましょう。
- 家庭での血圧測定: 病院で測る血圧だけでなく、**「朝起きてすぐ(排尿後・朝食前・服薬前)」と「寝る前」**の血圧を測ることが重要です。
最後に
当院では、経験豊富なベテラン管理栄養士が減塩食はもちろんのこと、糖質制限食をベースとした正しい栄養指導、さらに運動指導も行っています。
また、睡眠時無呼吸症候群の精査については、ご自宅で検査を受けることができます。
特に「朝の血圧」が高い場合(早朝高血圧)、寝ている間に血圧が高くなっている可能性が非常に高いと思われます。
「寝ている間だから気づかない」ということがないよう、朝の血圧を健康のバロメーターとしてチェックし、高い数値が続くようであれば、早めに病院を受診しましょう。
吹田市長野東19番6号
千里丘かがやきクリニック
院長 有光潤介