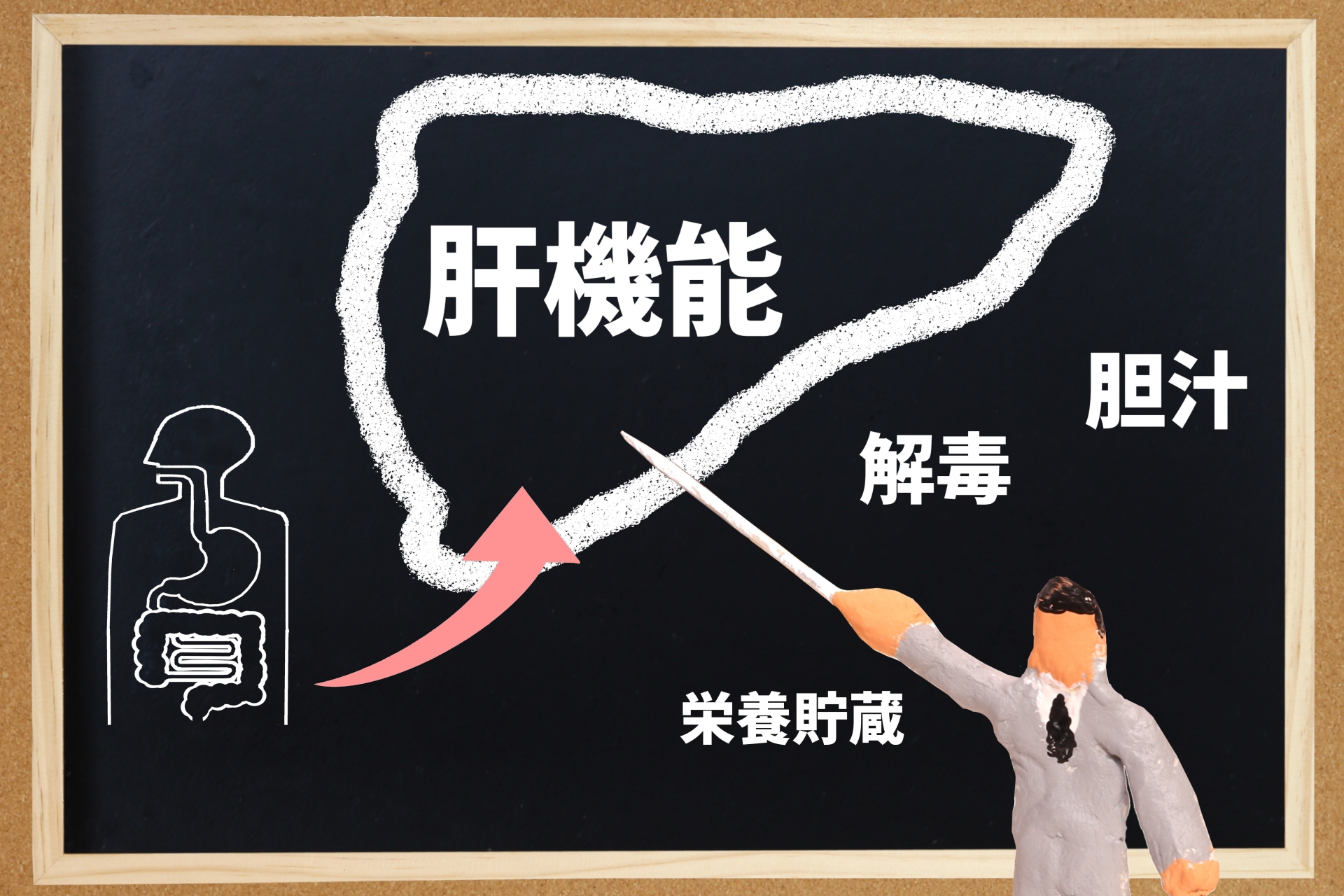2025年11月05日
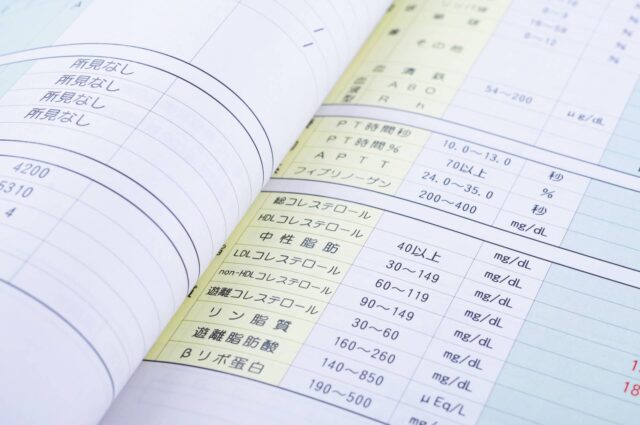
はじめに
年齢を重ねるにつれて、物忘れが増えたり、頭の働きが鈍くなったりすることへの不安は、多くの人が抱える共通の悩みです。健康に関する情報があふれる中で、私たちはしばしば「塩分を控える」「糖分を減らす」といった、特定の栄養素を「避ける」ことに焦点を当てがちです。
とりわけ「脂肪」は、健康の敵のように扱われることも少なくありません。
しかし、もしその「脂肪」こそが、私たちの脳の健康を守る鍵だとしたらどうでしょうか?
最近、日本の高齢者を対象としたある研究が、この常識に一石を投じる驚くべき結果を発表しました。
もしかすると、私たちが避けてきた特定の種類の脂質こそが、年齢による認知機能の低下から脳を守る、意外な味方なのかもしれません。
『脂質』の摂取量が多いほど、認知機能スコアが高かった
この研究は、地域社会で生活する154人の日本の高齢者を対象に行われました。
研究チームが参加者の日常的な栄養摂取量と認知機能を分析したところ、驚くべき事実が明らかになりました。
それは、1日の総脂質摂取量が多い人ほど、2種類の異なる認知機能テスト(認知機能全般を測るMoCAと、記憶力を測るWMS-DR)のスコアが高いという、統計的に有意な正の相関関係が見られたことです。
この結果は、「脂肪分の多い食事は不健康だ」という一般的な認識とは真っ向から対立するものです。しかし、この研究の背景には重要な文脈があります。
欧米では高齢者の肥満が問題視されることが多いのに対し、日本ではむしろ「痩せすぎ」が健康上の懸念となるケースが少なくありません。
このような背景を持つ日本の高齢者においては、適度な脂質の摂取が認知機能の維持に有益である可能性が示唆されたのです。
研究チームは、この発見を足がかりに、どの脂質が重要なのかを特定するため、さらに詳細な分析を進めました。
主役は『オレイン酸』という特定の脂肪酸だった
研究チームは、単に「脂質」という大きな括りで分析を終えませんでした。どの種類の脂肪酸が特に重要なのかを特定するため、段階的に調査を掘り下げていきました。
このような段階的な絞り込みは、一般的な相関関係から、より具体的で信頼性の高い結論を導き出すための科学的な手法です。
その結果、まず「一価不飽和脂肪酸(MUFA)」と呼ばれるグループが、認知機能と特に強い関連があることがわかりました。
そして、その中でも「オレイン酸」という特定の脂肪酸が、認知機能および記憶機能のスコアと最も強い正の相関を示した**のです。
オレイン酸は、健康的な食事法として知られる「地中海式ダイエット」の主要な構成要素であり、オリーブオイルに豊富に含まれることで有名です。
さらに、日本人にとってより身近な例として、長寿で知られる「沖縄の食生活」もまた、一価不飽和脂肪酸が豊富であることが指摘されています。
地中海式食事や沖縄の食生活が認知機能の低下を防ぐとされる理由の一つが、このオレイン酸にある可能性を、本研究は強く裏付けた形となります。
なぜこの研究は東アジアにとって画期的なのか?
この研究の最も重要な意義の一つは、日本の高齢者を対象に行われたという点にあります。
これまで認知機能と食事に関する研究の多くは、肥満対策として脂質の摂取を控えることが推奨される欧米で行われてきました。
食生活や体格が異なる日本人にも同じことが当てはまるのかは、明らかではありませんでした。
この研究は、欧米とは異なる食文化を持つ東アジアの高齢者にとって、脂肪酸の摂取が脳機能を維持するために重要であることを初めて科学的に示した点で画期的です。
研究者たちは、その結論を次のようにまとめています。
注目すべきは、本研究が日本のような東アジア地域において、高齢者の脳機能維持における脂肪酸摂取の重要性を指摘した初めての研究であるという点です。
結論
今回の研究は、日本の高齢者にとって、脂質、特にオレイン酸を豊富に含む食品を摂取することが、認知機能や記憶力を維持する上で有益である可能性を強く示唆しました。
もちろん、この一つの研究結果だけで食生活の全てを変えるべきではありませんが、これまで「悪者」と見なされがちだった脂質に対する私たちの見方を変える、重要な視点を与えてくれます。
この日本の研究は、高齢化に伴う「痩せ」が懸念される人々にとって、特定の「良質な脂質」は敵ではなく、脳の強力な味方になりうるという、新たな知識を私たちに与えてくれました。
普段使う調理油の種類を変えてみる、あるいは特定の魚を意識して選んでみる、そのような日々の小さな選択が、私たちの長期的な認知機能の健康を育むための、積極的な一歩となるのかもしれません。
参考論文
大阪府吹田市長野東19番6号
千里丘かがやきクリニック
有光潤介