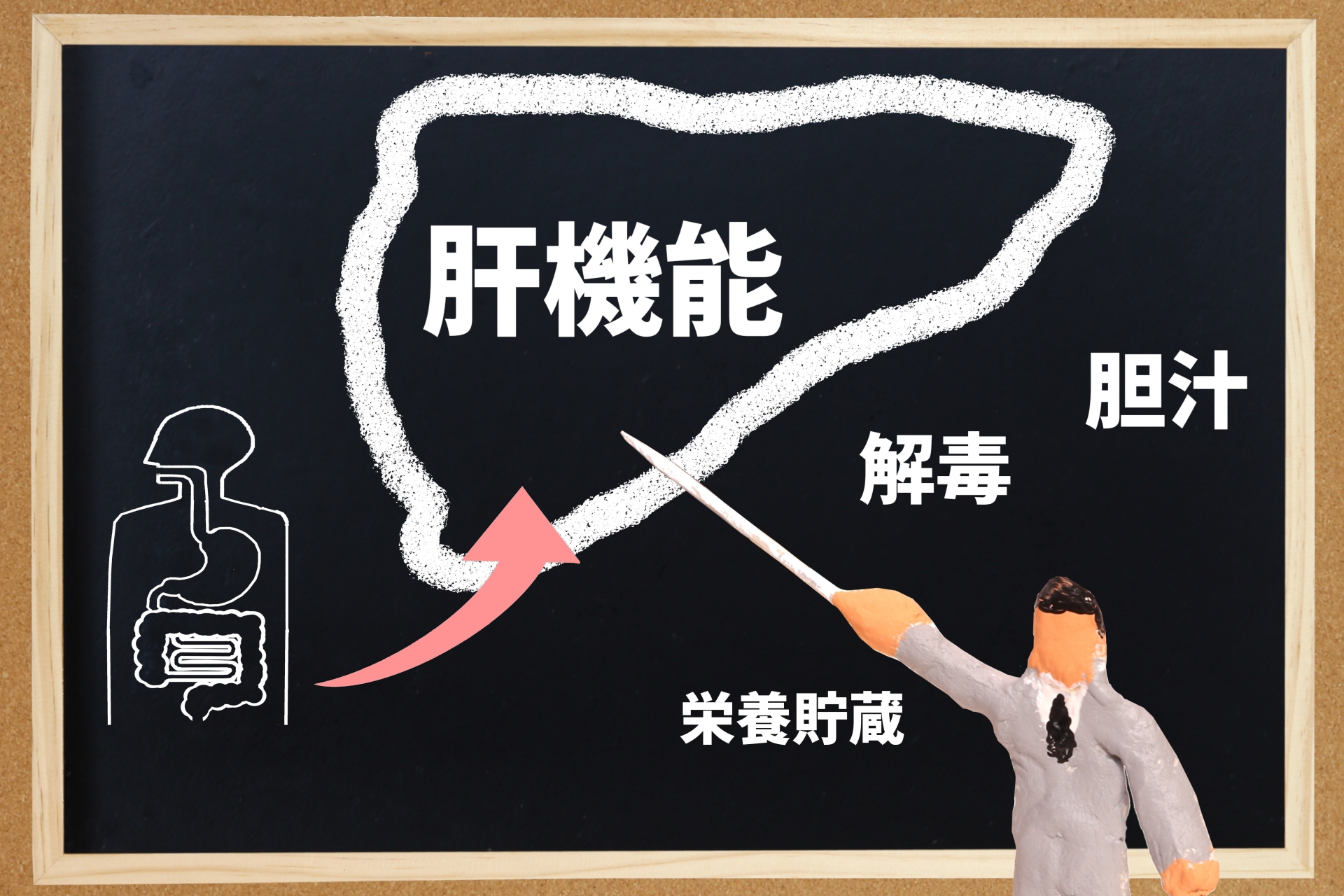2025年11月20日

「もっと野菜を」は正解か?日本人7割が知らない摂取量と塩分の意外な関係
「もっと野菜を食べましょう」― これは、私たちが耳にする最も基本的な健康アドバイスの一つです。
しかし、このシンプルな目標を達成できている日本人は、実はそれほど多くありません。
2024年に発表された最新の詳細な分析によると、2016年の大規模な「国民健康・栄養調査」のデータでは、国が推奨する1日の野菜摂取量350gをクリアしている成人は、わずか29%でした。
出典 Yuan X, Tajima R, Matsumoto M, et al. Analysing food groups and nutrient intake in adults who met and did not meet the daily recommended vegetable intake of 350g: the 2016 National Health and Nutrition Survey in Japan. J Nutr Sci. 2024;13:e12. DOI: 10.1017/jns.2024.5
しかし、この数字だけで「日本は野菜不足だ」と結論づけるのは早計です。
同調査によると、この29%という達成率は、アメリカ(10%)、イギリス(8%)、オーストラリア(8%)といった他の先進国と比較すると、実はかなり高い水準にあります。
では、問題の本質はどこにあるのでしょうか?
単に「もっと野菜を」と呼びかけるだけで、私たちの食生活は本当に向上するのでしょうか?
2万人以上の日本人を対象としたこの詳細な分析は、野菜摂取をめぐる複雑な実態と、特に日本の食文化に根差した「意外な罠」を明らかにしました。
このブログ記事では、その研究から見えてきた5つの重要な事実を解説します。

驚きの事実:日本人の7割以上が野菜不足
まず基本的な事実として、この研究は、調査対象となった成人21,606人のうち、71%が推奨される1日350gの野菜を摂取できていないことを明らかにしました。
具体的な数値を見ると、その差は歴然としています。
参加者全体の平均摂取量は281g/日でした。目標を達成できなかったグループの平均はわずか195g/日だったのに対し、達成できたグループの平均は495g/日と、目標を大きく上回っていました。
他国よりは高い達成率とはいえ、健康的な食文化で知られる日本においても、推奨される野菜量を摂ることは、大多数の人にとって依然として大きな課題であることがわかります。
まるで別人?野菜達成者の食生活は栄養の宝庫だった
野菜を十分に摂ることのメリットは、野菜そのものに含まれる栄養素だけにとどまりませんでした。
研究によると、野菜摂取量が350g以上のグループは、調査された27種類の栄養素のうち、実に25種類において摂取量が有意に高かったのです。
残りの2つの栄養素については、炭水化物の摂取量は有意に低く、ビタミンB12は両グループ間で有意な差はありませんでした。
食事全体の質にも劇的な差が見られました。
1日の食事記録に基づくと、野菜摂取量が多いグループの59%が、非常に多くの栄養素(17〜27種類)で国の推奨量を満たしていたのに対し、少ないグループで同等のレベルに達したのはわずか24%でした。
これは、十分な量の野菜を食べるという習慣が、より多様で栄養豊富な食生活全体の強力な指標であることを示しています。
最も意外な発見:野菜が多いほど「塩分」も多いというパラドックス
しかし、研究者たちがデータを深く掘り下げたとき、日本の健康的な食生活における前提を覆すようなパラドックスが浮かび上がりました。
他のほぼすべての点で健康的であったにもかかわらず、野菜を多く摂るグループは、少ないグループよりも有意に多くのナトリウム(塩分)を摂取していたのです。
なぜこのような逆説的な結果になったのでしょうか?
研究はその理由として、野菜を多く摂るグループが「調味料」の摂取量も有意に多かったことを指摘しています。
ほうれん草のおひたしにかける醤油、味噌汁の味噌など、私たちが野菜を美味しく食べるために使うまさにそのものが、この隠れた健康リスクに繋がっている可能性を示唆しています。
日本の食文化では、野菜を調理する際に醤油などの塩分を含む調味料が頻繁に使われるため、野菜の摂取量が増えると、それに伴って塩分摂取量も増加する傾向にあるのかもしれません。
この事実は、塩分の推奨摂取量を満たした人の割合にも表れています。
野菜が少ないグループでは10.3%が塩分目標をクリアしていましたが、多いグループではその割合が6.4%にまで低下していました。
この発見に対し、研究は「野菜の美味しさを保ちながら塩分を減らす調理法や保存方法を推進することが、将来の政策的介入に含まれるかもしれない」と提言しており、単なる個人の努力だけでなく、社会全体での取り組みの必要性を示唆しています。

「足す」だけじゃない。「引く」食生活への変化
野菜を多く食べる人は、単に普段の食事に野菜を追加しているだけではありませんでした。
彼らの食生活全体が変化し、特定の食品群の摂取量が自然と減少する傾向が見られました。
これは、栄養価の高い野菜が、いわゆる「エンプティカロリー」源となりがちな食品を食事から押し出す「クラウドアウト効果」を示唆しています。
特に、野菜摂取量が多いグループが「少なく」食べていたものは以下の通りです。
- 穀類 (Cereals): 米や小麦製品の摂取量が有意に少なかった。
- 卵類 (Eggs): 卵の摂取量も有意に低かった。
- 菓子類 (Savoury snacks and confectionaries): スナック菓子などの摂取量が有意に低かった。
- 飲料 (Beverages): ジュース類やアルコールを含む飲料全般の摂取量が少なかった。
この結果は、野菜を積極的に食事に取り入れることが、栄養価の低い食品の摂取を自然に減らし、結果として全体的により健康的な食生活につながるという好循環を生む可能性を示しています。
成功の鍵は「量」だけでなく「多様性」にあり
最後の重要なポイントは、1日350gという目標達成の鍵が、単一の野菜を大量に食べることではない、ということです。
研究によると、野菜摂取量が多いグループは、より「多様な」種類の野菜を、それぞれより多く摂取していました。
緑黄色野菜からその他の淡色野菜に至るまで、すべての野菜サブグループにおいて摂取している人の割合が高かったのです。
ここで興味深いのが「野菜ジュース」の存在です。
研究では、野菜ジュースが「推奨される野菜摂取量を満たすための重要な供給源となりうる」と指摘されています。
しかし専門家の間では、食物繊維が少ないことなどを理由に、野菜ジュースを野菜としてカウントすべきかについては議論があります。
多様性を追求する中で、ジュースのような手軽な選択肢も一つの方法ですが、やはり基本は様々な種類の「丸ごとの野菜」を摂ることが重要と言えるでしょう。
まとめ
日本の野菜摂取推奨量を達成することは、非常に栄養価の高い多様な食生活と密接に関連していることが明らかになりました。しかしその一方で、日本の食文化に根ざした調理法が、塩分摂取量の増加という「隠れた罠」を生んでいることも事実です。
塩分を控えつつ、野菜を上手く摂取する方法は、国立循環器病研究センター提唱する「かるしおレシピ」が有名です。クックパッドにもレシピが公開されています。
また、自己流で減塩方法にお困りの方は、当院の管理栄養士に是非ご相談ください。
吹田市長野東19番6号
千里丘かがやきクリニック
院長 有光潤介